こんにちは、孤独なライターです🎵
今回の記事から3回に分けて、「準動詞」という意味不明の文法についてみていきます。
今回の記事は
こんな方に向けた内容になります。
もくじ
はじめに

おそらく「準動詞」ときいても、何のことかわからない方が多いはず💦ですが「準動詞」という文法を学習していけば、聞いたことがある関連用語が出てきます。中学生のみなさんにとっては、理解しにくいかもしれませんが、いずれ学習することなので当ブログでトライしてください。中学英語にも大いに関りがあります。実は中学英語で習う「現在・過去進行形」と「受身表現」も、「準動詞」を使っています。準動詞ができるようになる大きいメリットは、「長い英文を理解できるようになる」ことです💡
- 「準動詞」とはなにか?
- 準動詞の「性質」と「種類」
- 準動詞の1つ 「(動詞の)原形」について
準動詞に強くなれば、受験生のみなさん、並び替え問題や英作文もよりできるようになりますので、がんばりましょう。
ではまいります、レッツゴー✨
準動詞とは?
g
動詞と深い関わりがある
「動詞」の理解なくして「準動詞」の理解なし。
「準」「動詞」なので、動詞と密接です。
①品詞上「動詞」に分類されない。
②しかし動詞の機能をもつ。
③文中で、名詞(句)・形容詞(句)・副詞(句)として働く。
つまり、「品詞的には完全な動詞ではないけれども、動詞と同じような使い方をしますよ」ということ。
そして、「動詞を使って、名詞(句)・形容詞(句)・副詞(句)を作れますよ」ということ。
だから、動詞をある程度知っていなければならないんです。
動詞を知らなければ、準動詞もわかりません。
以上の内容をきいてもピンときませんよね?
例を1つ出します。
「I study English.」
「ボクは英語を勉強します。」
この1文では、動詞が「study」で目的語が「English」ですね?
では動詞「study」を準動詞化させた文を2ついきます!
「I like studying English.」
「ボク、英語勉強するの好きだよ。」
この英文の動詞は「like」ですね?
「studying」ではありません。
そして「like」に対する目的語は、「studying English」です。
つまり、「英語を勉強すること」。
ここでは、「動詞」の「study」を「準動詞化」させて「名詞句」を作ってるわけです。
では次。
「To study English is important.」
「英語を勉強することは重要だ。」
この例文の動詞は「is」です。
「study」が動詞ではありません。
そして「is」に対する主語は、「to study English」です。
つまり「英語を勉強すること」。
①の例文と同じく準動詞で「名詞句」をつくって、「主語」にしているわけです。
「study」は、第1文型と第3文型をつくる動詞です。
だから「studying English」という準動詞を使った英文を組み立てることができます。
動詞の知識がなければ、準動詞の英文も理解できないとはこういうことです。
基本時制(過去形・現在形)は考慮しない
準動詞に「過去形」「現在形」はない。
例えば「これは過去の文だから、準動詞にしても過去形にしなきゃないのかな、、
だから準動詞にしても、-ed を語尾につけなきゃないのかなぁ?」
答えは、、「NO」です。
過去のことだから、準動詞にしても過去形で表すといったことはありません。
文の内容が「過去か現在か」といったことを示すのは、「準動詞」ではなく、あくまで「動詞/助動詞」です。
「I used to like studying English.」
「以前は英語勉強するのが好きだった。」
「Seen from a distance, he looked handsome. 」
「遠くからみたら、彼はカッコよく見えた。」
最初は、過去形の「used」が動詞です。
次は、過去形の「looked」が動詞です(Seenは過去分詞で過去形ではない)。
過去のことか、現在のことか、未来のことかは動詞・助動詞が決定します。
人称によって形が変わるということはない
動詞の性質をもつが、主語によって形を変えることはない。
動詞を準動詞にしたとき、主語が「私」とか「彼女」とか「彼ら」だから、それに合わせて一般動詞の語尾に「s」をつけることはしません。
例えば
「He likes studying English.」
「He likes to study English.」
「彼は英語を勉強することが好きです。」
「studying」の動作主は「he」です。
だからといって「studyings」とか「to studies」にはしません。
準動詞化するにあたって、人称の違いは考慮に入れません。
準動詞の種類
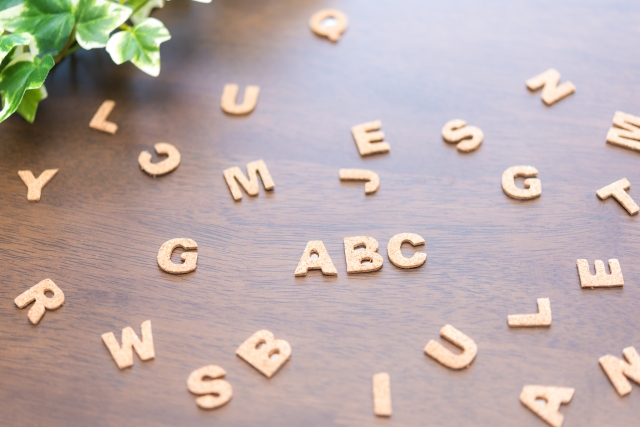
4種類です。
動詞の原形
動詞そのままの形。
準動詞の1つ、「動詞の原形」です。
過去形の「ーed」、三人称単数の「ーs」をつけない、なーーんにも動詞につけない「動詞そのままの形」です。
「動詞そのもの」です。
「You can make it.」
「キミならできるよ。」
「I saw him break the window.」
「彼が窓を壊すのを見た。」
「直ちに自分の仕事終わらせろ!」
「Finish your job immediately.」
赤文字はすべて動詞の原形です。
動名詞
動詞を「ーing」の形にしたもの。
「動名詞」とは、「動詞」を「名詞化」した「準動詞」です。
名詞にすることで、その部分を「主語」「目的語」にさせることができます。
元の動詞を「ーing」形にかえて、「動名詞」にします。
動名詞のコアイメージは、「その場感」「躍動感」です。
「Studying English is pleasing for me.」
「英語を勉強することは楽しい。」
「I remember seeing him there.」
「1年前彼とそこで会ったのを覚えているよ。」
不定詞
「to + 動詞の原形」の形。
「不定詞」の公式は、「to + 動詞の原形 」
コアイメージは「これから先のこと(可能性)」。
動詞を不定詞にすることで、「名詞句」「形容詞句」「副詞句」にすることができます。
「To talk in a library is not a good idea.」
「図書館で話すことはあまりいいことではない。」
「He seemed to have gotten over the disease.」
「彼は病気を克服したようだった。」
分詞
・「現在分詞」と「過去分詞」の2種類。
・コアイメージは、「実際の状態・行為・現実」。
不定詞が「これから先のこと」をイメージするのに対して、「分詞」のコアイメージは、「実際に起こっている・起こったこと」です。
実際に起こっていること。
動詞に「ーing」をつけて(動名詞と同じ)、分詞化することができます。
「Frankly speaking, his idea is not sensible.」
「はっきり言って、彼の考えは賢明ではない。」
現在分詞句=Frankly speakingは、副詞句として主節を修飾してます。
「He is playing the guitar in his room.」
「彼は自分の部屋でギターを弾いている。」
これ、いわゆる「現在進行形」の英文です。
つまり、「現在進行形」=「be」+「現在分詞」、といえます。
実際にされた(起こった)こと。
動詞を「ーed」化(これは規則変化)させて、分詞化することができます。
「Seen from a long distance, that rock looks like a statue of Buddha.」
「遠くから見れば、あの岩は大仏に見える。」
過去分詞句=Seen from a long distanceは、副詞句として主節を修飾してます。
「I was scolded by the teacher today.」
「今日先生に怒られたよ。」
これ、いわゆる「受け身」の文です。
受け身の文の公式は、「be」+「p.p(過去分詞)」でしたね。
では、まずは準動詞の1つ「原形」をみていきます。
準動詞 「動詞の原形」

「動詞の原形」を使うのは、3パターン。
助動詞の後は「動詞の原形」
主語が何であろうと、助動詞がきたら「 助動詞 + 動詞の原形 」。
「She will be a teacher sometime.」
「彼女いつか先生になるだろう。」
「Ken must go immediately.」
「ケンは今すぐ行かなければならない。」
主語が三人称単数だから「goes」ではなく、「must」という助動詞があるので動詞は原形の「go」になります。
知覚動詞・使役動詞の後にくる準動詞は「動詞の原形」
・「知覚動詞」………「see」「hear」など。
「見たり」「聞いたり」するといった類の動詞。
・「使役動詞」………「make」「have」など。
「人/ものに、~させる」という意味の動詞。
「第5文型」で「S V O C」の形をとります。
「 S は O=C である状態を V する 」が第5文型です。
知覚動詞・使役動詞では、「 C 」のところに「動詞の原形」がきます。
「I saw him get into the car.」
「彼が車に乗り込むところを見ましたよ。」
「get」は「動詞の原形」です。
「I made him read the book.」
「彼にその本を読ませた。」
「read」は「動詞の原形」です。
命令文
「Keep your station clear.」
「自分の持ち場をきれいにしておけ!」
「Have dinner, please.」
「夕食を食べてください。」
命令する相手は必ず「you」です。
(第三者に「指令」はくだせますが、「命令」はどう考えてもできません。)
この場合も、動詞は原形です。
まとめ

- 「準動詞」=動詞の機能を使って、名詞句・形容詞句・副詞句をつくれる。
- 「準動詞」=過去形とか現在形とか関係ない。
- 「準動詞」=人称は関係ない。
- 「動詞の原形」=動詞のもとの形。「助動詞の直後」「知覚動詞・使役動詞の後(補語として)」「命令文の動詞」にくる。
- 「動名詞」=「名詞句」のみをつくる。コアイメージは「その場感」。
- 「不定詞」=「名詞句」「形容詞句」「副詞句」をつくる。コアイメージは「これから先のこと」。
- 「分詞」=「形容詞句」「副詞句」をつくる。コアイメージは「実際の状態や行為といった現実」。
以上準動詞の基本事項と「動詞の原形」をみてきましたが、いかがでしたか?準動詞を使えるようになると、1文が長い英文を理解できるようになります。というのは、準動詞が使われることで英文が長くなることがよくあるからです💡大学入試といったアカデミックな英文を読むなら、なおさら準動詞の理解は必須です。大学受験生のみなさんはとくに、準動詞の勉強をしてください🎵
関連記事のリンクをのせて終わりにします。
― To the Finest Hour ―
原形.jpg)
動名詞・不定詞.jpg)
分詞.jpg)
動名詞・不定詞-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
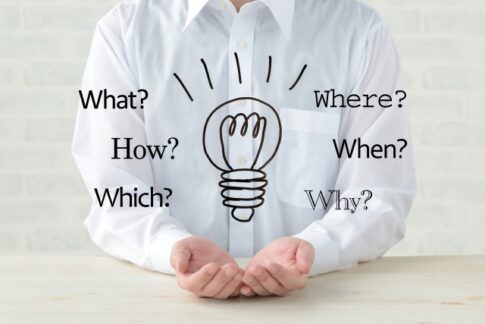

.jpg)
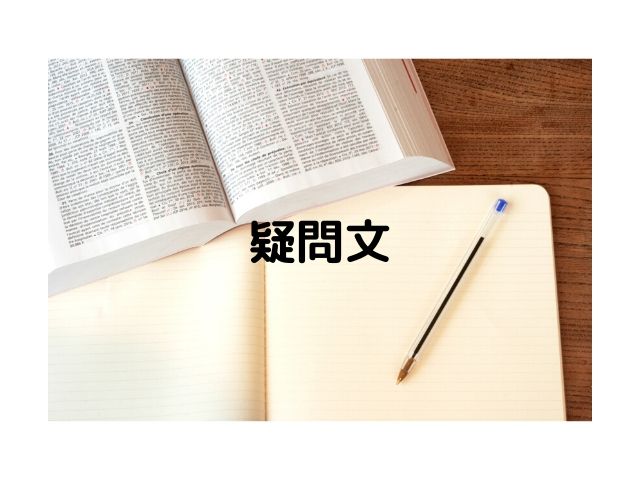
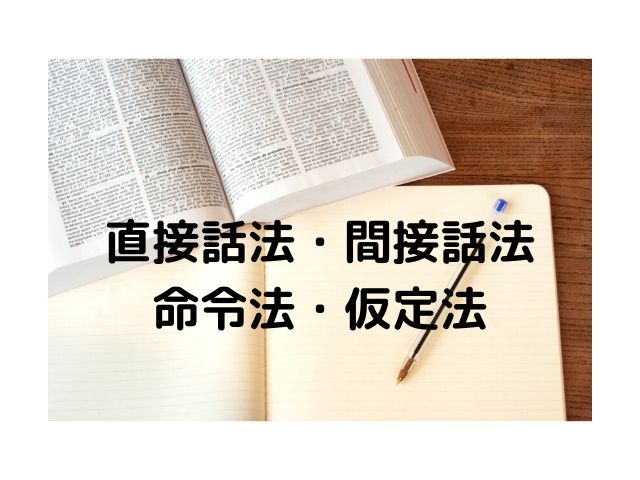

完了形.jpg)
.jpg)
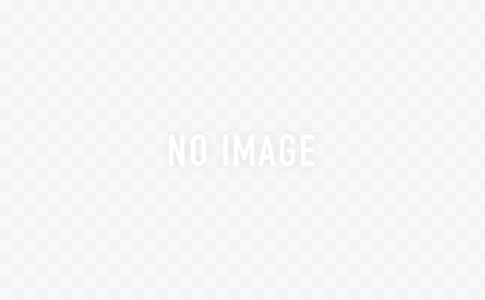



・英語学習初心者
・「動名詞」「不定詞」「分詞」とかって何?